今回は、このブログそのものについて書きます。
背景
かなり遡りますが、昔むかし、筆者がノンポリだった頃、友人に誘われて、経済評論家の大前研一さんを囲む学生・若手社会人の集まりに行ったことがあります。10数人の参加者の中で、筆者はノンポリ過ぎて、明らかに浮いていました。筆者は黙り込んでいたのですが、意見を求められ、トンチンカンなことを言って、その場の空気感から「しまった」と思いました。でも、大前さんは、筆者のトンチンカンな発言に対して、筆者にわかるような返答をしてくださったんです。さらに、親父ギャグも披露してくれました。
それまでの大前さんは、取っつきにくい印象でしたが、そのとき「この人はいい人だな」と思いました。

筆者と大前さんの接点は、それぐらいなので、実際に大前さんがいい人なのかどうかを保証しているわけではありません。
それは「たまたま」で、状況や立場が異なれば違う印象になった可能性もありますが、筆者はそれから、大前さんの著書を次々と読むようになりました。そこから、関心が広がっていき、自由主義的な経済観を持つようになりました。
もし、そのとき、大前さんの印象が悪ければ、反対の結果になっていたかもしれません。
筆者の社会人スタートは、福祉の世界でした。
福祉の世界は、社会主義とまでは言いませんが、リベラル、「大きな政府」的な先輩が殆どだったんです。筆者は先述のように「小さな政府」的な考え方ですから、たまに、政治や経済の話をするときには、筆者は周りの人とは全く意見が合いませんでした。
でも、リベラルな先輩達は、寛容で、自分たちと異なる意見も熱心に聞いてくれました。アフターファイブに、そうした議論をするのは、楽しいことでした。
名前の由来
さて、ブログのことです。
まず、この「減税派MMTのススメ」のネーミングの由来です。
「減税派」というのは、筆者の基本的なスタンスですね。
筆者の趣味はDTM(Desk Top Music)です。DTMは、集中して没頭するときは時間を忘れますし、スランプのようになって「当分、DTMはやりたくない」というときもあります。
このブログを始めたのは、そういうDTMスランプのときで、ふと、ブログを書くことで気分転換しようとも思ったのです。
筆者は、DTMの情報を集めるためにTwitterをしていました。そこで、MMTの話題がよく出ていることに気がついていました。

DTM系の人って、MMTが好きな人が多いような気がします。
筆者の考え方とは、かなり違ってそうだな、と、先入観をもっていましたが、「MMT現代貨幣理論入門(L・ランダル・レイ.著)」を読んだときに、「MMTは、違った意見ではなく、違ったレンズ(視点)である」と書いてありました。また、
本書の目的は、特定の政策を押しつけることではない。本書は、「大きな政府」支持者も「小さな政府」支持者も利用可能である。私自身が進歩主義寄りなのはつとに有名だが、MMT自体は中立的である。
L・ランダル・レイ. MMT現代貨幣理論入門
とも書いています。
それまで、「MMT」対「反MMT」って、お互いが決して相容れることがない無益な議論をやってると思っていましたが、いや、MMT的な切り口で「小さな政府」を説明できるんじゃないかなと思ったんです。
日本版MMTって土台が陰謀論なので、誰かを悪者にすることから始まりますが、本物のMMTは、良い意味でリベラルです。
MMTの主張にも「なるほど」と思うところも多々あります。「なるほど」とは思えないところもあります。

ミイラ取りがミイラに
社会人なりたての頃、リベラルな先輩達と楽しく議論したことは良い思い出なので、MMTな人たちとも、楽しく意見交換できるはずだ、という思いました。というか、ネットではなく実際の社会では、むしろ「大きな政府」志向の人たちに、いい人が多い印象です。
保守ということ
「保守」対「リベラル」という対立軸があります。
いろんな定義ができると思いますが、筆者は、
みたいな定義もできるのではないかと思います。
その定義では、筆者は保守となりますが、その場合の「日本の伝統」とは「寛容」「中庸」「礼節」「和を以て貴しとなす」みたいなものが土台になるかと思います。
筆者は、学生の頃は、そういった価値観を完全にバカにしていました。でも、社会人になって、年数を重ねて、だんだんと、「寛容」「中庸」「礼節」などの価値の大切さがわかってきました。
昔、大前研一さんが、ノンポリな筆者を「バカなやつ」と無視していたら、あるいは、「大きな政府」主義者になっていたかもしれません。

ここからは、自戒を込めて書きます。
日本は民主主義の国ですから、意見が多数派になれば勝ちで、ならなければ負けです(勝ち負けという表現がいいのかどうかは別として)。味方を増やすゲームです。
知識や知恵は味方を増やすための武器であって、大切なのは「武器の性能」ではなく「目的と使い方」です。
SNS的な「論破してやった。バカめ!」では、相手を感情的に頑(かたく)な、意固地にするだけです。多数派形成など、おぼつきません。
自分の意見を持ってバトルするような人は全体の少数です。それを黙って見ている人のノンポリの殆どは、「正しいかどうか」じゃなくて「そんな言い方しなくていいのに」みたいな判官贔屓な不快感を持って見ています。知識がある者が、知識のない者をボコボコにするのは、いじめにしか見えません。
そうやって知識をひけらかす奴ほど、本人は気がつかないだけでみっともないです。

自分もDTMだけのためにTwitterをしていた頃、タイムラインに、いつものバトルが流れてきたときはそう思っていました。
筆者は、SNSで「こんなこともわからないのか」と相手を罵倒している人を見ると、「民主主義とは、味方を増やすゲームだというルールも知らないのか」と思います。
「もっと勉強しろ」など捨て台詞をする人は、頭が悪いのかと思います。一時的に自分が優越感に浸ってスカッとするだけで、バトルの相手の背後に、多くの中立者が見ていることにも気がまわらないのです。それらの中立者は、バトルするだけの知識がないから黙っているので「もっと勉強しろ」では、自分が批判されているように感じてしまうのではないでしょうか。

自分の悪印象を振りまいています。
北風と太陽の話で言えば、風の強さを競うことに夢中で、目的を忘れてしまったようなものです。
意見が異なる者は、自分に都合のいいところだけ拾い読みしますので、相手が「なるほど」と受け入れるように、意見を書くのは、相当に工夫が要ります。それを、「こんなことも理解できないのか」は罵倒するのは、その人の説明能力の低さをPRしているようなものです。

偉そうに書きましたが、自分も耳が痛いです。
話が少しずれていますが、そのあたりが「MMT的な切り口で」と考えた理由だったです。
ただ、筆者の最大の経済的関心は「どうしたら豊かになるか。それには経済成長」に集約されますが、MMTは経済成長には余り関心がないようなのです。そこで、「MMT的な切り口で」は、最初の頃の数本の投稿で終わってしまいました。
ブログのスタンス
このブログの投稿も、もうすぐ50本になります。
こんなに続くとは思っていませんでしたもので、ネーミングも安直に決めてしまいました。
続いた理由としては「今、考えていること。今、そう思うこと。調べたこと。」というスタンスで「100%正しいことを書こうとしない」ことが良かったんじゃないかと思います。100%正しいことを書こうとしたら、いつまでも書けなくなってしまうからです。
過去の投稿を読むと「こんな風に考えていたのか」ということもあります。幹の部分では大きな変化はありませんが、枝葉の部分では結構、変化しています。
筆者は、経済はド素人ですが、それだけに「経済のどこがわかりにくいのか」「自分だったら、どのように説明されたらわかりやすいか」が、素人ブログの役割かなと思います。

それ以外に得意分野がない
明らかな誤字脱字だったり、データが間違っていたり、(プライバシーなど)表現上の問題に気がついたり、したときは、訂正しますが、学びの成長の記録でもあり、それ以外はそのまま残して、また、新たな投稿で新たなことを書けばいいわ、と考えています。
このブログで書いていることは、筆者が、仕事、家族や友人との付き合い、趣味、の合間の、少しの時間だけで書いているだけの素人考えに過ぎません。でも、その仕事、家族や友人との付き合い、趣味、は貴重な人生経験であり、そこから滲み出るものは、机上の知識だけで得られないものがあります。専門的な人のサイトはそれで、素人のブログはそれで、それぞれ役割があると思います。
このブログを読んでくださる方がいて、いろんなことを考えるきっかけにしていただければ嬉しいです。そういう中で、もちろん筆者の考えも当然変わっていきますし、いいかんじで、少しずつ一つの方向(多数派)に集約されていくようなスタイルが、筆者が理想とする「保守」です。
ネトウヨであろうがパヨクであろうが、お互いを罵倒し合うような姿は、保守としての生き様から遠いです。一方、リベラルであっても、日本の伝統的な美徳「寛容」や「中庸」や「礼節」を大切にする姿勢は、筆者が理想とする「保守」なのです。
「保守」論は、また、機会があれば書きたいと思います。

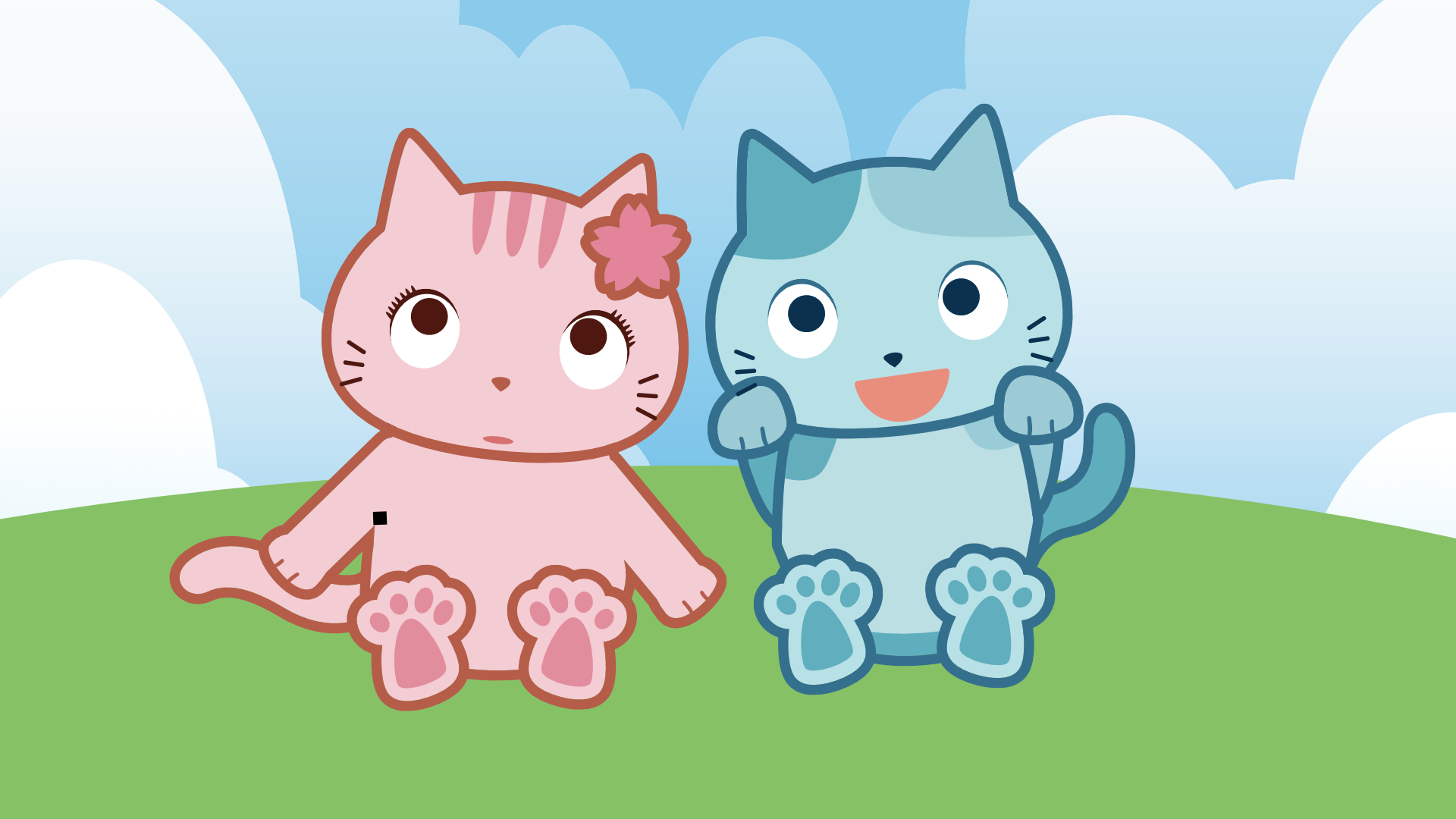
コメントをどうぞ!